��������Ǝ�ޔ̔��K���ɘa�̕��Q��T��
2010�N10��9��
�ڎ�
�P�D�u��������v�Ƃ�
�u��������v�Ƃ́A�x�O�^�̑�^�X��V�����ƑԂ̃R���r�j�G���X�X�g�A�ȂǂƂ̋����Œn��̏��K�͂Ȍl���X�̌o�c�����藧���Ȃ��Ȃ�p�Ƃ��i�ނ��Ƃɂ��A�����ɔ������ɍs�����Ƃ��ł��Ȃ���ʎ��[1]�ł��鍂��҂Ȃǂœ��X�̐H���i����p�i�̍w���ɍ�����Ă���l�X�̂��Ƃ��w���Ă���B
���ɍ���Ɖߑa����������������ʋ@�ւ̉^�s���R�����R���ɂ����āA��������̖��͐[���ł��邪�A�s�s���ł��V���b�^�[���X�X��[2]�̉e�����ē���̔��������s�ւɂȂ����Ɗ����Ă��鍂��҂͑����B
��Ƃ����\���ɂ͒�R�����邽�߁A�u��������v�Ƃقړ��l�̒�`�ŁA�u����������v�Ƃ������t���g���Ă���B�o�ώY�ƏȂ̌����2010�N�i����22�N�j5���ɂ܂Ƃ߂��u�n�搶���C���t�����x���闬�ʂ̂����������v���ł́A�S���́u��������ҁv�̐����600���l�Ɛ��v���Ă���B�Ȃ��A�����ł́u��������ҁv�Ƃ́A���ʋ@�\�̕ω����ʖԂ̎�̉��ƂƂ��ɁA�H���i���̓���̔�����������ȏɒu����Ă���l�X
�ƒ�`����Ă���B�܂�600���l�Ƃ������v�l�́A���t�{��2005�N�i����17�N�j�ɍs�����u����҂̏Z��Ɛ������Ɋւ���ӎ����������v�i�S����60�Έȏ�̒j��3��l�ɃA���P�[�g�j�ɂ����āA�u�Z��ł���n��ŕs�ւɎv������C�ɂȂ����肷�邱�Ɓv�i�����j�Ƃ��āu����̔������v��I�������l�̊����i16.6���j��60�Έȏ�̍���Ґ��i3,717���l�j���悶�ĎZ�o���ꂽ���v�l�ł���B
�������A���̃��|�[�g�Ŏ��グ�����e�[�}�͂����܂Łu��������v�ł���A600���l�Ɛ��v�����u��������ҁv�Ɠ��`�ƕ߂炦��̂͂�◐�\�����錙��������B�u�n�搶���C���t�����x���闬�ʂ̂������������v�ɏ�����Ă���u��������ҁv�̒�`�́A���̃��|�[�g�ł́u��������v�̑������ɂقڍ��v���Ă�����̂́A600���l�Ƃ������v�l�͒P��60�Έȏ�̍���Ґ��ɓ���̔��������s�ւƊ����Ă��鍂��҂̊������悶�ĎZ�肵�����̂ł���B�ȑO���R���ł̐����ɂ����Ĕ������͕s�ւł���A���Ɉꌬ�̏��X�܂ʼn��L���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������͑��������͂��ł���B�܂��A�X�[�p�[�܂Ő��S���[�g����������Ă��Ȃ����ɏZ��ł��Ă��A�O�o���獢��ȍ���Ƌ��҂͏��Ȃ��炸���悤�B�������A�ߔN�ɂ����ĎR���̉ߑa�����i�W���A���������x���Ă���Ă����Ⴂ�������オ���𗣂�A����Ƌ����邢�͍���҂݂̂̐��т������������ƂŁA����̔������ɍ�����������Ă���l�����������Ă���B�܂��A�ߗׂ̏��X���p�Ƃ������ƂŁA�����܂ő���L���Ȃ��Ɣ��������ł��Ȃ��l�X�������Ă���B���̂悤�ɁA�ߔN�ɂ�����Љ�\���̕ω��̉e�����ē���̔������ɐV���ȍ�������Ă��܂��Ă���u��������ҁv���A�����ł͊����āu��������v�Ƒ����������ƂƂ������B
[1]��ʎ�ҁF�@�����ł͎����Ԓ��S�̎Љ�ω��ɂ����āA�^�]�Ƌ��⎩�Ɨp�Ԃ������Ȃ�����҂�q���A��Q�҂�Ꮚ���҂ȂǁA�����Ԃ����l�X�ɑ��Ēn��ړ��̐�����Ă���l�X���w���Č�ʎ�҂ƌĂԁB������ʋ@�ւ������p�ł��Ȃ����߁A�����ԎЉ�ɂ����ĎЉ�I�Ɏア����ɂ���A������ʋ@�ւ̐��ނ��i�ޒn����R���ɂ����Ă͓��Ɍ�ʎ�҂̖��͐[���ł���B
[2]�V���b�^�[���X�X�F�@���[�^���[�[�V�����̐i�W���ɔ�����^�X��x�O�^�X�܂̑䓪�ŁA���X�X�ł͏��X�̕X���i�݁A�V���b�^�[�����낵���X�܂��ڗ����ނ������X�X���w���ăV���b�^�[���X�X�ƌĂԁB
�Q�D��������̋K��
�ł́A��������͂ǂ������̂��낤���B��������҂̐����A60�Έȏ�̍���Ґ�3,717���l����Z�o�����n�搶���C���t�����x���闬�ʂ̂��������������班���������Ă݂����B
�@a. ���v����1
�܂��A�n��ł̔����������X�s�ւł��A�Ⴂ�����Ƒ����x���Ă��Ă��ꂽ����퐶���ɏd��Ȏx��͏o�Ȃ��ł��낤���Ƃ���A����P�g�҂��邢�͍���v�w�݂̂̐��т�����̎Z�o�̕ꐔ�Ƃ��Đ��v�������Ă݂�B
2005�N�i����17�N�j���������ɂ��ƁA65�Έȏ�̍���P�g���т�386�����сi�l�j�A�v��65�Έȏ�ōȂ�60�Έȏ�̍���v�w���т�449�����тƂȂ��Ă���B���̑S��1,284���l�ɁA��̏Z��ł���n��œ���̔��������s�ւɎv���Ă��鍂��҂̊���16.6�����悶��ƁA��������̋K�͂�213���l�Ɛ��v�����B
�@b. ���v����2
����A60�Α��70�Α�ɂȂ��Ă��܂����C�ŁA�o�������Ƃ����܂��ɂȂ�Ȃ��l���������邱�Ƃ���A65�Έȏ�̍���҂��ꗥ�ɔ�������̐��ݓI�ȕꐔ�S�̂Ƃ݂�̂͒�R������B�����ŁA80�Έȏ�̍���P�g���тƍ���v�w���т̂ق��A��Q�҂̒P�g���т�����̐��ݓI�ȕꐔ�Ƃ��Đ��v�������Ă݂�B
2005�N���������ɂ��ƁA80�Έȏ�̍���P�g���т�106�����сi�l�j�A�v�ȂƂ���80�Έȏ�̍���v�w���т�28�����тƂȂ��Ă���B�܂��A��Q�Ҕ����ɂ��ƑS���̐g�̏�Q���Ґ��͖�366���l�ŁA���̖�1�����P�g���������Ă���Ƃ݂��Ă��邱�Ƃ���A���̐��͖�37�����сi�l�j�Ɛ��肳���i����P�g���ѐ��Ƃ̏d���܂ށj�B�����̐��������Z����ƁA���ݓI�Ȕ�������̕ꐔ�Ƃ��āA��170�����сA���v��200���l�Ƃ����������������яオ���Ă���B���̐����ɁA��̒����ŏZ��ł���n��œ���̔��������s�ւɎv���Ă���u80�Έȏ�̊����v�ł���17.6�����悶��ƁA��������̋K�͂�35���l���x�Ɛ��v�����B
�@c. ���v����3
�ߑa���ȂǂŐl����50%�ȏオ65�Έȏ�̍���҂ɂȂ�A�W���̎���������A�������ՂȂǎЉ�I���������̈ێ�������ɂȂ����W���̂��Ƃ��w���āA�u���E�W���v�ƌĂԁB�ʈĂƂ��āA���̌��E�W���ɍݏZ����l�X������Ƃ��đ����A���̐��𐄌v���Ă݂�B
���y��ʏȂ�2006�N�i����18�N�j�x�ɍs�����u�W�������v�ɂ��ƁA10�N�ȓ��������͂�������ł̉\���̂���W���͑S����2,620�W������B���̏W���̐��ыK�͕��z�ʂ̕��ϐ��ѐ����琄�v����ƁA�����̏W���ɍݏZ���鐢�ѐ���33,270���сA1���т�����l����2�l�O��Ƒz�肷��ƍݏZ�l����6�`7���l���x�Ɛ��v�����B
�@d. ���v����4
�n��̏��K�͏����X�܂̌o�c���x���Ă����̂́A��Ɏ�ނƂ����̔̔��ɂ����v�ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���B���Ɏ�ނ̔̔��Ɋւ��ẮA1998�N�i����10�N�j����2003�N�i����15�N�j�ɂ����Ď�ޏ����ƖƋ��ɌW��K���ɘa���i�K�I�ɐi�߂��A����5�N�ԂɎ�̓X�̓]�p�ƁE�|�Y��2��4039��[3]�ɒB���Ă���B���X���\�Ȑ��v�ł͂��邪�A���̓]�p�ƁE�|�Y����2��4��̎�̓X�����I�ɗ��p���Ă����ł��낤���т̂����A����P�g���тƍ���v�w���т̊������甃������̐��𐄌v���Ă݂�B
������̓X�̕��ϓI�ȋߗח��p���ѐ���400���тƉ��肵[4]�A���̂���65�Έȏ�̍���P�g�E����v�w���т̊����ł���14.3���̐��т�����܂œ���I�ɗ��p���Ă���������̓X��2��4�猬�ɋy�ԓ]�p�ƁE�|�Y�̉e�������Ƃ���ƁA���̐���137�����т̖�212���l[5]�Ɛ��肳���B
[3]�@�S��������̑g�����������ׂ̎����u�]�p�ƁE�|�Y�y�ю��H�E�s���s���ҁiPDF,880KB�j�v�ɂ��B
[4]�@����13�N�x�̍��Œ��u��ޏ����Ǝ҂̌o�c���Ԓ��������v�ɂ��ƁA��ޔ̔��̋Ƒԕʂň�ʏ����ꐔ��70,967��A���̔N�ԏ������ʂ̓r�[����3,721,398kl�A������756,072kl�ƂȂ��Ă���B����A���Œ��u���̂������v�ɂ��ƁA����13�N�x�̐��l1�l������̎�ޔ̔��i����j���ʂ̓r�[����46.1l�A������9.3l�ƂȂ��Ă���B���������āA��ʏ����X�ɂ����鑍�ڋq���͖�8�疜�l���x�ƌ����܂�A1�X�܂�����ł�1,100�l���A�����1���т����蕽�ϐl��2.71�l�i����12�N�����������j�Ŋ���Ɩ�400���тƂȂ�B
[5]�@����12�N���������ɂ�����A65�Έȏ�̍���P�g���ѐ�303�����сA�v��65�Έȏ�ōȂ�60�Έȏ�̍���v�w���ѐ�366�����т̊������Z��B
�ȏ�A��������̒�`�����m�łȂ���ɁA���̐���c�����邱�Ƃ͓��v�̐�������荢��ł��邪�A���Ȃ����ς����Ă�10���l���琔�\���l�K�́A��`�̘g���L�����200���l�K�͂̐l�X����������Ƃ��āA����̔������ɂ����č����̎Љ�\���̕ω��ɂ�镾�Q���Ă���Ƒz�肳���B
�R�D��ޏ����ƖƋ��ɌW��K���ɘa�Ƃ��̉e��
�����X�ɂƂ��Ď�ނ́A�������������v���ɂ��D�ꂽ���i�̈�ł���B���ۂɁA�ߏ��́h��p�����h�̎������o���_�ɁA�l�X�ɋƑԕω����Ȃ���n��ɍ��t���Ă����l���X����ϑ����B�����������X�́A���炭�u��ޏ����ƖƋ����x�v�̊������v�Ɏ���āA�������������Ȃ��n��̂Ȃ��ŏ��K�͌o�c�Ȃ���Œ�q�Ƃ̕t�����������Ő����Ȃ��炦�Ă����B
�Ƃ��낪�A���i�����������Ȃ����������Ƌ����x�ɂ��K���͏���҂ɂƂ��ă}�C�i�X�ł���A�K�����ɘa���ׂ��Ƃ���Љ�\���ω��̓������o�u���o�ς̕���ƂƂ��ɋN�������B�����āA1998�N�i����10�N�j����2003�N�i����15�N�j�ɂ����Ď�ޏ����ƖƋ����x�͊ɘa�E�p�~�ւƐi��ł������B����ɂ��A�X�[�p�[��R���r�j���ł���ނ̔̔����L����A�h���b�O�X�g�A�[��z�[���Z���^�[�ł͉��i�������N����A���Ƀr�[���ƊE�ł͂������Ȕ��A�����O�̃r�[���̕��y���㉟�����A����҂͉��i�ʂɂ����đ傢�ɋK���ɘa�̉��b���邱�Ƃ��ł����B
�������A����Ŏ�ޏ����ƖƋ����x�̋K���ɘa�́A�ߗׂɂ�����V���ȋ����X�̒a���Ɖ��i�����̖u�������������ƂŁA�]�O�̌�p�����I�Ȓn���̌l���X�̑������낤�����邱�Ƃɂ��q�������͂��ł���B���̌��ʁA�����n�����X�̕X��p�Ƃ��i�Ƃ���ƁA�K���ɘa�͈��̏���҂ɑ��Ēቿ�i���̉��b�������炵���Ɠ����ɁA��p�����ɉ���Ă��炤���Ƃœ���̔��������\�ƂȂ��Ă�����ʎ�҂ł��鍂��҂Ȃǂ������������Ƃ������Q�������炵�����ƂɂȂ�B
��ޏ����ƖƋ��ɌW��K���ɘa�͂ǂ̂悤�ɐi�߂��A���̌��ʁA��ނ̈�ʏ����X�Ȃ�тɊ֘A������H���i�����X�̐��͂ǂ̂悤�ɕω����Ă������̂��A�ȉ��Ō��Ă݂悤�B
�@(1) ��ޏ����ƖƋ��ɌW��]�O�̋K���[�u
��ނɊւ���Ƌ����x�͕��G�ł��邪�A�]�O�̒�����X���W����̂́u��ʎ�ޏ����ƖƋ��v���x �ł���B��ʎ�ޏ����ƖƋ��̊�g�́A�l����Ƌ�����̓�ʂ��甛���Ă����B
- �s��ʎ�ޏ����ƖƋ��̎��������v���t
-
- a. �l��� �i2003�N(����15�N)9���P���p�~�j
- �\���̔��ꂪ���݂��鏬���̔��n��ɖƋ��g������A���̘g���ł����Ƌ�����Ȃ��B
�Ƌ��g �� �i �l�� �� ��l�� �j �| �����X��
�\1�@��l�� �n�� �����O 1998�N�x
�iH10�N�x�j1999�N�x
�iH11�N�x�j2000�N�x
�iH12�N�x�j2001�N�x
�iH13�N�x�j2002�N�x
�iH14�N�x�jA�n��i��s�s�n��j 1,500�l 1,450�l 1,400�l 1,300�l 1,200�l 1,100�l B�n��i���s�s�n��j 1,000�l 950�l 900�l 850�l 800�l 750�l C�n��i���̑��̒n��j 750�l 700�l 650�l 600�l 550�l 500�l [��] �Ȃ��A2�������i�i�K�I�Ȋɘa���m���Ɏ��{����ړI�ŁA��l���ɂ��v�Z�������l�Ɗ����X����2�����悶�����l�i�������Œ�1�A���5�j�̂����ꂩ�傫�����l��N�x���Ƌ��g�Ƃ���j�́A����11�Ƌ��N�x�������Ĕp�~���A����12�Ƌ��N�x�ȍ~�́A�l����̓K�p�����ŔN�x���Ƌ��g���Z�肷��B
- b. ����� �i2001�N(����13�N)1��1���p�~�j
- �\���̔���ƒ��ߎ�̓X�Ƃ̋��������̊�ȏ�ł��邱�ƁB
- A�n��:�@100m �i�������l��30���l�ȏ�̓s�s�ō��ŋǒ����w�肷���v�w����500m�ȓ��ɂ��鏤�ƒn��ɂ��Ă�50m�j
- B�n��:�@100m
- C�n��:�@150m
[��] �Ȃ��A�u��^�X��ޏ����ƖƋ��v�Ƃ����Ƌ��g������A�X�ܖʐς��P���u�ȏ�̑�^�����X�܂ɑ��ẮA��ʂ̎�̓X�ɑ��ēK�p��������������̗v���i�Ƌ��g�y�ы�����j��K�p���Ȃ��ŖƋ����t�^�����B
�@(2) ��ޏ����ƖƋ��ɌW��K���ɘa�̐��i
1990�N�i����2�N�j�O��̃o�u���o�ϕ����A�o�ς̒���������ɑ��ē��{���{�́A�o�ϐ�����}�邽�߂ɋK�����v�𐄂��i�߂Ă������B1995�N�i����7�N�j�ɐ��{�́A�Z��E�y�n�A���E�ʐM�A���ʁA�^�A�ȂǑ���̕���ɂ킽�鐔�獀�ڂ̋K���ɘa�荞�u�K���ɘa���i�v��v�i�t�c����j�\�����B���̌�����������v��̉��肪�s���A1998�N�i����10�N�j�ɂ́u�K���ɘa���i3���N�v��v���A2001�N�i����13�N�j�ɂ͊ɘa������v�ւƈ�����ݍ����̂ɕς�����V���ȁu�K�����v���i3���N�v��v�����\���ꂽ�B�����Ă����̌v��̐��i�ɂ��A���{�̎Љ�ƌo�ςɂ����锲�{�I�ȍ\�����v���������邱�ƁA���ێЉ�ɊJ���ꎩ�ȐӔC�Ǝs�ꌴ���ɑ��������R�Ō����ȎЉ�o�σV�X�e����n�o���邱�ƁA���O�K���^�̍s�����玖��`�F�b�N�^�̍s���ɓ]�����Ă������ƁA�����ڕW�Ƃ��Ď����ꂽ�B
��ŋy�ю�ޔ̔��̋K���ɌW��鍑�Œ��ł́A1998�N�i����10�N�j�x�ȍ~�A�K���ɘa���i3���N�v��Ɋ�Â��A5�N�ԂŎ��������v���ł���l����i���l�����Ƃɔ̔��Ƌ���t�^�j�̒i�K�I�ɘa�����{���ꂽ�B������̓X������̋����i50�`150m�j�ɂ͖Ƌ����Ȃ��Ƃ����������2001�N�i����13�N�j1���ɔp�~����A�l����ɂ��Ă��ŏI�I��2003�N�i����15�N�j9���ɔp�~���ꂽ�B
���Q�l�����Œ� ���k����u��ޏ����ƖƋ��ɌW��K���ɘa�̏��v
�@(3) �K���ɘa�O��ɂ������ޔ̔��Ƃ̓���
�������H���T�[�`�́u��ޔ̔��Ƃ̓|�Y���������v�i2004�N8���j�ɂ��ƁA1994�N�i����6�N�j4������2004�N�i����16�N�j3���܂ł�10�N�Ԃɂ����āA�|�Y�����͑S�Y�Ƃł݂�Ό����������Ă��邪�A����r�[�����̉����⏬�����s����ޔ̔��Ƃł́A�����X����������Ƃ����B
��ޔ̔��Ƃ̓|�Y�����́A���̒�����10�N�ԂŁA������269���A������1,209���A���v1,478���������Ă����i�}1�Q�Ɓj�B���ɓ|�Y����������2000�N�i����12�N�j�x�̃s�[�N���ɂ�185���ɒB���A�ȍ~2�N�Ԃ͌����X���ɂ��������A2003�N�i����15�N�j�x�ɂ�161���ƍĂё����ɓ]���Ă���B
�Ȃ��A�|�Y������Ƃ̋K�͕ʂł݂�ƁA�N���ʂł�1���~������63.7���B�]�ƈ����ʂł�10�l������91.8���ƂȂ��Ă���A���̋Ǝ�̓|�Y�����ɔ�ׂĂ����K�͗�Ǝ҂̓|�Y���ڗ����đ����Ȃ��Ă���B
�}1�@��ޔ̔��Ƃ̓|�Y�����y�ѕ����z�̐���
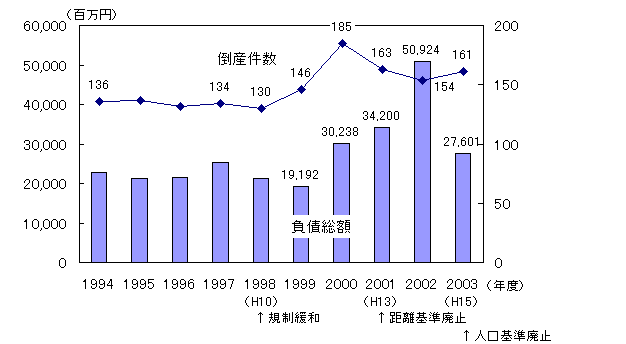
�i�����j�������H���T�[�`�u��ޔ̔��Ƃ̓|�Y���������v���
�܂��A���Œ���2002�N�i����13�N�j�x��2006�N�i����18�N�j�x�ɍs�����u��ޏ����Ǝ҂̌o�c���Ԓ��������v�ɂ��ƁA��ނ̋Ƒԕʔ̔��ꐔ�ɂ����āA��ʏ����X�i��ʎ�̓X�j�̐��͒�����5�N�Ԃ�70,967�ꂩ��71,530��ւƋ͂��ɑ����Ă͂��邪�A���̊ԂɑS�̂̔̔��ꐔ�͖�43�����������Ă���A���ʂƂ��Ĉ�ʏ����X�̊����͕���13�N�x�ɂ�70����������18�N�x�ɂ�50���ɂ܂Ō������A�t�ɃR���r�j�G���X�X�g�A�̊�����17������25���ɑ��債�Ă����i�}2�Q�Ɓj�B
����A�Ƒԕʍ��v�������ʂ��݂�ƁA������5�N�ԂőS�̂ł�19���������Ă���ɂ�������炸�A��ʏ����X�̍��v�̔��ʂ�3,798,216kl����2,282,407kl�ւ�40�����������Ă���B�����ł́A��ʏ����X�̍��v�̔��ʂ͕���13�N�x��55������18�N�x�ɂ�28���܂Ō������A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�₻�̑��i�ʔ̓X��z�[���Z���^�[�E�h���b�O�X�g�A���܂ށj�̊������}�g�債�Ă���B
��ޏ����Ƃ̋K���ɘa��ʂ��āA�̔��ꐔ�͑傫���������A���̑������i������5�N�Ԃ�40�����j�͑��������ʂ̑������i��19�����j�̖�2�{�ɒB���Ă���B����ŁA�����̑����Ŕ��ꂠ����̏������ʂ͌������i�S�̂�-17�����j�A���Ɉ�ʏ����X�ł�-40�����Ɣ��ɑ傫����������ł���B
�}2�@��ނ̋Ƒԕʔ̔��ꐔ�y�э��v�����ʂ̕ω��i����13�N��18�N�j
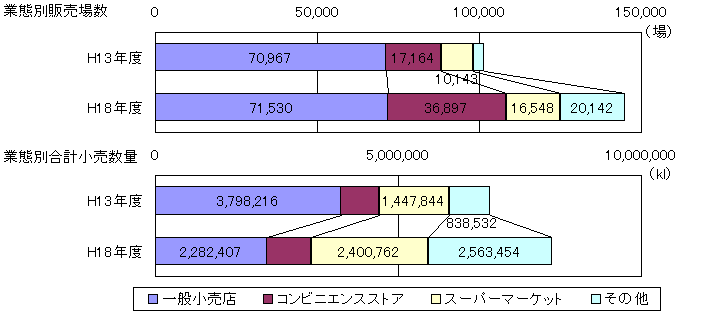
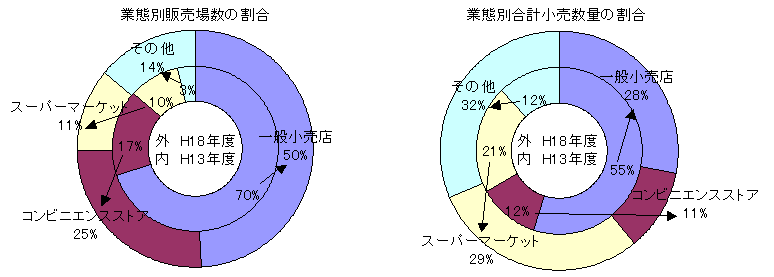
[��] ����13�N�x������18�N�x�����ł͋Ƒԕʂ̕��ނ��قȂ�B����13�N�x�́u���������g���v�Ɓu�_�Ƌ����g���v�́A�u�X�[�p�[�}�[�P�b�g�v�Ɋ܂߂�B����18�N�x�́u�ʔ̓X�v�u�Ɩ��p�v�u�z�[���Z���^�[�E�h���b�N�X�g�A�v�́A�u���̑��v�Ɋ܂߂�B�Ȃ��A�u�S�ݓX���v�Ɓu���̑��v�͂�������u���̑��v�Ƃ���B
�i�����j���Œ��u��ޏ����Ǝ҂̌o�c���Ԓ��������v���
2002�N�i����13�N�j�x����2006�N�i����18�N�j�x�܂ł�5�N�ԂŁA�S���̈�ʏ����X�i��̓X�j�̔��ꐔ�͋͂���0.8���������Ă��邪�A�n��ɂ���Ă��̕ω��ɂ�����݂����i�}3�Q�Ɓj�B���i30.6�����j�A�D�y�i14.1�����j�A�F�{�i6.2�����j�A�֓��M�z�i5.7�����j�̊e���ŋ��Ǔ��ł͔�r�I�傫���������Ă������ŁA�����i-14.8�����j�A�����i-11.5�����j�A����i-10.9�����j�A�����i-10.7�����j�Ȃǂ̊Ǔ��ł͑傫���������Ă���B
���̊Ԃ̐V�K�Ƌ��̎擾������ԊҌ�����������Ȃ����ߒ肩�łȂ����A��ʏ����X����R���r�j�G���X�X�g�A�ւ̈ڍs���i�n�������A��^�X�ւ̏W�������i�n�������ȂǁA�n�悲�Ƃ̎�����f����Ă�����̂Ǝv����B�܂��A�S�̂Ƃ��Ĉ�ʏ����X�̔��ꐔ���������Ă��Ă��A���̊Ԃ̓|�Y��������M���ɁA�����̈�ʏ����X������I�ɑ����������Ƃɂ����̂Ƃ͍l����A�X�E�p�ƂƐV�K�o�X�̊����ȓ���ւ�肪�i���ΓI�Ȍ��ʂƂ��đ�����ׂ��ł���ƍl������B
�ȏォ��A�����̈�ʏ����X�i��̓X�j�ł͋K���ɘa�̐��i�̉e�����āA�|�Y�݂̂Ȃ炸�X��p�Ƃ��i�W���Ă��邱�Ƃ��M����B�����̏���҂ɂƂ��ẮA�K���ɘa�ɂ��̔�������������戵�X�܂̑����Ɖ��i�ቺ�̃����b�g�������炳�ꂽ�B����������ŁA�n��̏��K�͏����X�܂ł͌o�c�����藧���Ȃ��Ȃ�X��p�Ƃ��i�݁A�ꕔ�̏���҂ɂ͋ߗׂ̏��X�������Ȃ邱�Ƃœ���̔��������s�ւɂȂ�Ƃ������Q���������Ɛ��������B
�}3�@���ŋǕʂ̈�ʏ����X�̔��ꐔ�̕ω����i����13�N��18�N�j
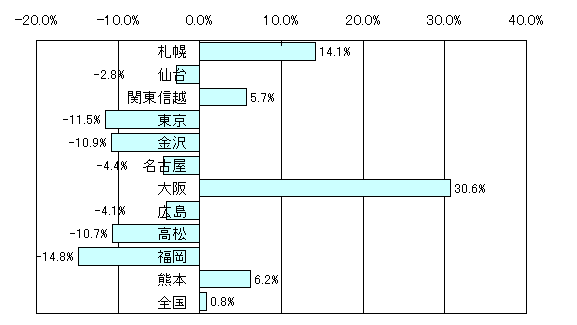
[��] ���Œ��̊e���ŋǂ̊NJ����ɂ��ẮA���Œ��z�[���y�[�W�̍��ŋǂ̃y�[�W�Ŋm�F�̂��ƁB
�i�����j���Œ��u��ޏ����Ǝ҂̌o�c���Ԓ��������v���
�@(4) ���H���i�����X�̓���
���ɁA�o�ώY�ƏȂ́u���Ɠ��v�v�ŁA�����ƑS�̂Ƃ��̂����̈��H���i�����Ƃɂ��Ď��Ə����̐��ڂ��݂�ƁA������̎��Ə�����1991�N�i����3�N�j�ȍ~�͖������N���ɂ����Ĉꗥ�Ɍ����𑱂��Ă����i�}4�Q�Ɓj�B�N���ϐL�ї��i�������j���݂�ƁA�����Ə����Ƃ�1999�N�i����11�N�j�܂ł͂��̌����X���Ɏ��~�߂���������������A1999�N�ȍ~�͍Ăі��N�̌��������g�債�A����2002�N�i����14�N�j�ȍ~�̈��H���i�����Ƃɂ����鎖�Ə����̌��������������傫���Ȃ��Ă���i�N����-3.5���̌��j�B
���̊Ԃɂ����鍑���ƌv�ŏI����x�o�i���ځj�̔N���ϐL�ї����݂�ƁA1990�N��̓o�u���o�ς̕���ɂ�����̗������݂������������A2000�N�ȍ~�͎��������̌X�����݂���B���������āA���H���i�����Ƃ�2002�N�i����14�N�j�ȍ~�̎��Ə����̑啝�Ȍ����́A�i�C�̉e���Ƃ������́A��ޏ����ƖƋ��ɌW��K���ɘa�ɂ��e���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
�}4�@�����ƑS�̂Ȃ�тɈ��H���i�����Ƃ̎��Ə����̐���
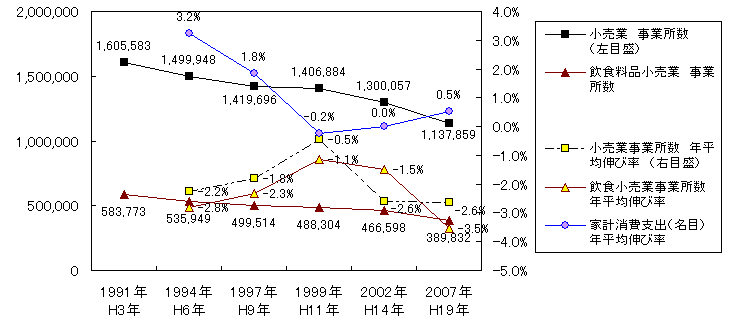
[��] ����9�N�ȑO��11�N�ȍ~�̏��Ɠ��v�����ɂ�����Ƒԕ��ނ��قȂ邽�߁A���H���i�����Ƃ̕���9�N�ȑO�̒l�͈ꕔ�ɐ��v���܂ށB
�Ȃ��A����6�N��11�N�͊ȈՒ����B�i�����j�o�ώY�Əȁu���Ɠ��v�v�A���t�{�u�����o�όv�Z�m���v���
�S�D�܂Ƃ�
�K���ɘa�́A�ߋ��̓��{�o�ς̐����ߒ��ɂ����Đ����I�ɓ�������Ă����K���A�܂萭�{�⎩���̂Ȃǂ���߂Ă��鋖��m�F�A�����A�͂��o�Ƃ������s��ɂ�����l�X�Ȑ�������菜������������ɂ߂��肷�邱�Ƃɂ��A��ƂȂǖ��Ԏ��Ǝ҂̎��R�Ȋ�����i�삵�A���{�o�ς̍���̍X�Ȃ�i�W��}�邽�߂Ɏ��g�܂�Ă����o�ύ\�����v�̈��i�ł���B
�K���ɘa�𐄐i���邱�ƂŁA�V���Ȋ�Ƃ̎s��Q���𑣂��A��Ɗԋ����ɂ��T�[�r�X��i���̌���Ɖ��i�̒ቺ�A�ٗp�̊g��Ƃ������Љ�I�E�o�ϓI�����b�g�������炷���Ƃ����҂����B
- �� �K���ɘa�������炷�Ɗ��҂���郁���b�g
- �V�K�Q����Ƃ̊g��ƁA���������ɂ��o�ϊ����̊�����
- �ٗp�@��̑���
- ��Ɗԋ����ɂ��T�[�r�X�̉��P��i���̑��l���A�i���̌���
- ���i�̒ቺ�◿���̌n�̒e�͉��ɂ�����҃R�X�g�̒ጸ
- �s���R�X�g�̍팸
- ��Ɗ����̌���������
- etc
����A�K���ɘa�ɂ��e���Ƃ��āA�}�C�i�X�ʂ������炳���\�������邱�Ƃ�F�����Ă����K�v������B
- �� �K���ɘa�������炷�\���̂���f�����b�g
- �V�K�Q���ɂ��p�Ƃ�|�Y�����̑���
- ��Ɗԋ����̌����ɂ��A�Ǝ��Ԃ̑���A�c�Ǝ蓖�ẴJ�b�g
- �R�X�g�팸�ɂ�鋋�^�̒ቺ�A���X�g���̐i�W
- �I�g�ٗp���x�̕���A�h����Վ��ٗp���ɂ��A�Ƃ̕s���艻
- ���}�ȃR�X�g�J�b�g�ɂ����S���̒ቺ�A�����i�̔���
- etc
��ޏ����ƖƋ��ɌW��K���ɘa�́A��K�͎��{���^�X�܂̐V�K�Q���������炵�����ƂŁA���i�����ɍ~�Q������Ȃ��Ȃ����n��̒���������̓X�̕X��p�Ƃ�U���������Ƃ͖��炩�ł��낤�B���̌��ʂƂ��āA�ꕔ�̎s��������������̗J���ڂ����ł��낤���Ƃ́A�K���ɘa�̃f�����b�g�Ƃ��Ĉ�ʂɑz�肳��Ă���ȏ�̕��Q�ł���B
��ޏ����ƖƋ��ɌW��K���ɘa�́A�P�ɉ��ď�����͕킵�������E�s���̍l������i�ߕ��Ɍx����炵�A���{�炵���A�܂���{�Ɠ��̏����K��Љ�K���A�����╶���̂�����̉��l���������ׂ��ł��邱�Ƃ��������Ă���B
